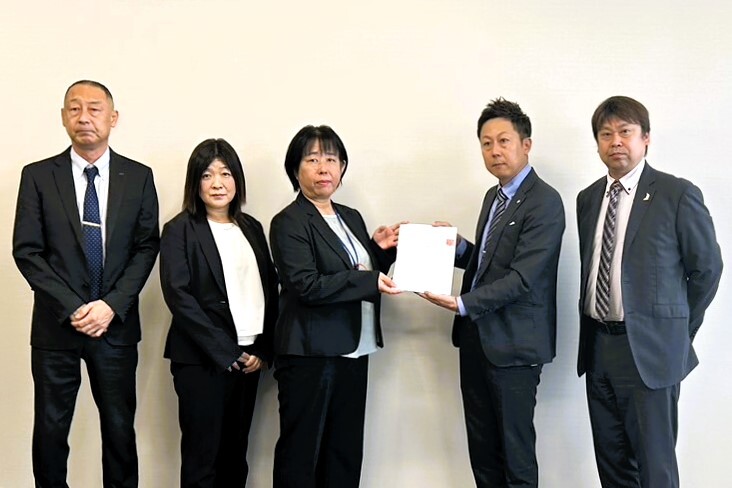政策要請
2026(令和8)年度 自治体政策・制度予算に対する要請
<要請日>
| 地区 | 自治体名 | 要請日 | 要請方法 |
|---|---|---|---|
| 堺地区 | 堺市 | 2025年11月6日(木) | 市長及び担当者との懇談 |
| 泉州地区 | 高石市 | 2025年10月14日(火) | 副市長との懇談 |
| 和泉市 | 2025年10月14日(火) | 市長との懇談 | |
| 泉大津市 | 2025年10月14日(火) | 副市長との懇談 | |
| 岸和田市 | 2025年10月14日(火) | 市長との懇談 | |
| 忠岡町 | 2025年10月14日(火) | 町長との懇談 | |
| 泉南地区 | 貝塚市 | 2025年10月29日(水) | 副市長との懇談 |
| 泉佐野市 | 2025年10月29日(水) | 市長との懇談 | |
| 泉南市 | 2025年10月29日(水) | 市長との懇談 | |
| 阪南市 | 2025年10月29日(水) | 副市長との懇談 | |
| 田尻町 | 2025年10月29日(水) | 町長との懇談 | |
| 熊取町 | 2025年10月29日(水) | 副町長との懇談 | |
| 岬町 | 2025年10月29日(水) | 町長との懇談 |
<要請と回答(全体)> ※2026年3月頃更新
| PDF 堺地区協議会 2026年度政策・制度予算に対する自治体要請回答(PDF) PDF 泉州地区協議会 2026年度政策・制度予算に対する自治体要請回答(PDF) PDF 泉南地区協議会 2026年度政策・制度予算に対する自治体要請回答(PDF) |
大阪南統一要請
(1)震災における対応について <継続>
阪神・淡路大震災から30年が経過しました。この間、2011年「東日本大震災」・2016年「熊本地震」・2024年「能登半島地震」と、大きな災害が日本各所で発生しました。また南海トラフ巨大地震の30年内発生確率も80%と修正され、上町断層においても地震発生確率が高くなっているところです。大阪南地域は、縦断的に海・山に囲まれている地形となっていることから、津波対策及び土砂崩れ対策等、多岐に亘る震災対応が求められます。各自治体においては、その対応を含めた様々な地域防災訓練が実施されていると考えますが、その実施状況や実施する旨の住民周知、また年間どの程度の訓練が実施されているのか、さらに各自治体で工夫されている防災訓練も含めてお示し頂きたい。
(2)各自治体における少子化対策について <継続>
2024年の出生数は、前年の72.7万人より4.1万人減少した68.6万人となり、予想より早い段階で70万人を割る結果となりました。2025年には65万人程度になると予想されており、少子化=人口減少の傾向は悪化していると言えます。各自治体では、子育て世帯を対象とした給食費の無償化や医療無償化の対象者拡大、また小児科医療の充実など様々な子育て施策を実施されていると承知しています。しかし、各自治体で同じような施策を行っている状況もあるように感じています。少子化対策や教育施策について、他の自治体と差別化を図るために、独自的に実施している施策や事業をお示し頂きたい。また広域的に行っている施策があれば、併せてお示し頂きたい。
(3)子ども食堂ネットワークについて <継続>
最近の子ども食堂は、地域交流の居場所づくりやコミュニケーションの場としても機能しています。一方、昨今の物価高騰により、運営側に大変な負担が掛かっている状況となっています。連合大阪南地域協議会としても、フードドライブを展開し、一助になればと取り組みを進めていますが、到底改善するまでには至らない状況です。各自治体としてもフードドライブの取組みを積極的に推進頂き、地元業者とタイアップする等、実質的な支援の展開をお願いしたいと考えています。
ついては、各自治体で実施しているフードドライブ支援や運営支援策をお示し頂きたい。また、地域で支えてくれている子ども食堂運営者側と、各自治体との意見交換ができるネットワーク会議の構築を求めます。設定できないのであればその理由も併せてお示し頂きたい。地区独自要請
堺地区協議会
(1)堺臨海地区における防災対策の強化について <継続>
令和2年8月に大阪湾沿岸における最大規模の高潮に係る浸水想定区域が公表された。この公表結果に基づき、ここ数年で、様々な施策を講じているが、堤防の嵩上げ等の海岸保全施設の増強計画について、早期整備に向け大阪府に対して継続して要望すること。
加えて、臨海地域における、地震・津波、高潮による人的被害を防止するための避難計画について、地域で働く方のみでなく、7-3区内の公園利用者も含めた避難経路の確保に向け、事業所間連携の促進に向けた働きかけを積極的に行い、具体的かつ実効性のある施策の実現に向け取り組むこと。(2)公共交通の維持活性化について <継続>
全国的に公共交通の存廃に関する報道がなされる等、交通事業者は厳しい経営状況にある。生活に欠かせない公共交通機関の代表であるバス・路面電車事業に対し、今後も国の交付金活用や市の予算措置により、引き続いての支援をお願いしたい。
特に交通弱者の生活交通確保・社会参加促進の観点に加え、バス・路面電車事業回復に向けての大きな投資でもあるノンステップバス・車両導入に対しては、国の動向に左右されず、「堺市生活交通改善事業計画」に基づき、計画通り進めていただきたい。(3)泉北ニュータウン活性化対策について <継続>
現在、堺市SENBOKUスマートシティ構想において協働で事業を推進し、企業・団体・地方公共団体などの会員を募り活性化を図るとしている。そのなかで新しい移動手段の導入により、幅広い世代が距離や利用シーンに応じて最適な移動手段を選択できる環境をめざすとし、AIオンデマンドバスの実証実験が行われているが、利用者からは非常に好評であり、本格運用を求める声が多い。交通不便地域という事もあり、幅広い年代での利用者が増えており、地域住民にとっては必要なインフラとして認識されている。
しかし、AIオンデマンドバス事業は採算をとるのが難しく、民間委託では、不採算路線からの撤退も十分に考えられ、地域の魅力向上や発展には繋がらない。
AIオンデマンドバス事業については企業任せの要素が強く、「南海電鉄が主体となって実施するもの」として回答が示されている。
(4)熱中症対策について <新規>
本年もこれまでと同様に、命にかかわるような危険な猛暑となった。企業への対策啓蒙を継続していただくと同時に、堺市独自あるいは周辺自治体と共同により熱中症対策を進めていただきたい。
具体的には、人が集中しうる場所へのスポット的な冷風扇等の配置、信号待ちなど逃げ場がない箇所への日よけの設置など検討をすすめていただきたい。泉州地区協議会
高石市
(1)臨海工業地帯の防犯について <継続>
高砂1号線の中央分離帯は樹木の剪定を防草シートの活用で視界が広がり交通事故防止に繋がっています。樹木の適切な剪定と定期的なメンテナンスは、犯罪の隠れ家や不備な場所の形成を防ぐために重要です。また、近年、樹木の成長が早く年2回の剪定では安心・安全な歩行者の移動が困難のため、市民が快適に移動できる環境を維持するためにも、歩行者・自転車ルートにおける樹木の剪定実施回数を増やすこと。
(2)防災について <新規>
近年、南海トラフ地震などの切迫性に加え、台風や集中豪雨による浸水・土砂災害の危険性が高まっております。高砂(臨海部)の労働者は連絡橋「高石大橋」が唯一の交通手段であり、災害により通行不能となった場合には、事業者の避難・救助活動に甚大な支障をきたす恐れがあります。臨海部地域における防災対策を強化するため、避難経路の多重化、緊急輸送路の整備、代替ルートの確保を早急に検討・推進されるよう要請いたします。防災行政無線、メール配信、スマートフォンアプリなど、市民一人ひとりに迅速かつ的確に情報が届くよう確実な情報伝達手段を構築すること。
和泉市
(1)新住居表示の整備について <継続>
現在、旧の住居表示の地域において、救急や消防の事案が発生したときに目的地が分かりにくい、到着に時間がかかっています。また災害時における避難指示に関しても「〇×町」よりも 「〇△町〇丁目とした方が避難の必要であることが伝わりやすいと考えられます。また、救急や消防の事案が発生したときに目的地がわかりにくく、到着に時間がかかることが懸念されるため、住民の意向や要望を踏まえた上で、丁寧な対応と住民との合意が出来次第、新住居表示の整備をすること。
(2)教育施設の老朽設備の環境整備について <継続>
市の公立各種施設では、トイレやフェンスなど設備の老朽化が進んでいると認識しています。特にトイレについては、施設によっては早急に整備が必要な状態であると感じています。子どもの健康や成長の観点からも、利用しやすい環境整備の実行計画や予算編成について具体的な計画を示すこと。
(3)防災情報の周知活動拡大について <補強>
昨今の自然災害による市民の安全への懸念を抱いており、LINEなどのSNSを活用した情報展開に加え、デジタルを活用できない方々への情報伝達の強化が必要と考えます。そこで、町会未加入者やLINE未登録者へ防災ガイドマップを全戸配布するなど防災周知活動を強化すること。また、町会等未加入者の周知方法についても併せて示すこと。
(4)市民の移動手段(公共交通機関)対策について <補強>
市民の移動手段である公共交通機関について、一部の路線で減便などの運行縮小が発生していることを心配しています。市として、今後同様の状況が再発した場合、どのような取り組みを検討しているのか見解を述べること。
また現在、公共交通機関の企業では深刻な人手不足に陥っています。特に赤字路線と呼ばれる路線について、市としてのオンデマンドバス等の具体的な対応策や赤字路線に対する予算編成を示すこと。(5)リチウムイオン電池について <新規>
リチウムイオン電池はモバイルバッテリーや、スマートフォン、パソコンなど、充電できるさまざまな製品に使われていますが、リチウムイオン電池が原因とされるパッカー車や清掃工場の火災や発火などの事故は年々増加しています。また、メディアによるハンディファンやモバイルバッテリーの発火の検証等により、市民が不安な状態に陥っています。市として、回収や処理方法等の政策を具体的に示すこと。
泉大津市
(1)地域医療体制の確立について <継続>
泉大津急性期メディカルセンターへの交通手段の確保が問題となっています。ふれあいバスの運行ルート見直しによる渋滞緩和や周辺の道路環境整備を行い、利用者に円滑な運行と安全な環境の確保に向けた取り組みを行うこと。
(2)地域振興策について <継続>
シーパスパークなど西側地域だけでなく、市全体の歴史的な資産や特徴を活かし、市民との協力を得て地域の振興と活性化を目指した施策を示すこと。また、近年シーパスパーク利用者の違法駐車が増加しており、周辺環境の安全確保や快適な利用の妨げとなっています。安全かつスムーズに駐車いただけるよう公園駐車場の利用する取り組みを行うこと。
(3)安心安全な街づくりについて <継続>
自転車の交通ルールの順守が市の交通安全教室の実施で向上してきています。継続実施して頂き自転車・電動キックボードのマナー面も指導や取り締まりを行い、地域の安全強化に向けた取り組みを行うこと。
岸和田市
(1)防災について <継続>
近年、南海トラフ地震などの切迫性に加え、台風や集中豪雨による浸水・土砂災害の危険性が高まっております。ちきりアイランド(阪南2区)は連絡橋「岸之浦大橋」が唯一の交通手段であり、災害により通行不能となった場合には、住民や事業者の避難・救助活動に甚大な支障をきたす恐れがあります。臨海部地域における防災対策を強化するため、避難経路の多重化、緊急輸送路の整備、代替ルートの確保を早急に検討・推進されるよう要請いたします。防災行政無線、メール配信、スマートフォンアプリなど、市民一人ひとりに迅速かつ的確に情報が届くよう確実な情報伝達手段を構築すること。
(2)緊急車両の到着時間短縮に向けた新住居表示と道路改善について <継続>
岸和田市における救急車出動件数は年々増加し、令和6年(2024年)には年間14,000件、1日平均38件と過去最多を記録しました。災害や急病など緊急時において、救急・消防車両が迅速に現場へ到着することは、市民の生命を守るうえで非常に重要です。古い・読みにくい・設置場所が不適切な住居表示により住所の特定に時間がかかることから、分かりやすい新住居表示の導入や狭隘道路の拡幅や交差点改良、標識・道路照明の充実、AIやデジタル技術を活用した最適配車システムの導入などを進め、緊急車両の迅速な到着体制を確立すること。また全国的に道路の陥没事故が年間1万件を超える規模にのぼっており、老朽化インフラ(下水道管・道路舗装)の点検・更新・補強強化を計画的に推進すること。
(3)競輪場の処遇について <補強>
競輪事業は本市にとって安定的な財源確保の柱として地域経済や市民サービスの維持に欠かせない事業であり、2030年に予定されているIRの開業は、娯楽産業の競争環境に影響を及ぼす可能性がある中、競輪場としても独自性と社会的役割をより明確にし、市民の理解と支持を高める必要性があります。また地球温暖化や異常気象の影響により、熱中症リスクや天候不良など施設の在り方にも再検討が求められております。競輪場が公共性を持つ施設であることを踏まえ、再生可能エネルギ一の導入、省エネ設備など脱炭素社会の構築に資する施設運営や、地域のスポーツ振興や福祉、教育防災等に果たしてきた社会貢献活動を一層可視化し、来場者の満足度向上と地域からの信頼確保に取り組むこと。開催業務等包括委託による運営においても、民間企業との連帯支援体制を強化し、持続可能な公営競技の発展に向けた施策を積極的に推進すること。
(4)山林の管理について <補強>
近年の豪雨災害では山間部において土砂崩れや倒木による被害が発生し、交通遮断や住宅被害を招き、森林整備と管理強化は喫緊の課題です。森林整備事業への予算拡充、地域住民や団体と連携した協働管理体制の構築を推進し、市全体の安心・安全確保に努めること。
(5)交通インフラについて <新規>
①岸和田市八阪町交差点において、松浪硝子工業から交差点に向かう右折車(大阪方面)の事故が多発しています。八阪町交差点 に向かう230号線は車幅も狭く、地下道もあり歩行者や自転車などの往来も多く常に危険な交差点であるため、大阪方面に向かう信号機に右折矢印の設置、もしくは時差信号を導入すること。
②岸和田市岸の丘町3-2-25 ゆめみヶ丘横交差点において事故が多発しています。近隣に大学などの施設もあり見通しがよい道路のためスピードを出す車が多いためだと考えられます。信号機の設置、もしくは道路上に注意を促す塗装をすること。
③岸和田市三田町「藤池後援南」の交差点において、近隣の会社(全星薬品工業等)の退社時間において(夕方5時30分前後から1時間程度)藤池公園南交差点に向かう右折車で渋滞が発生します。交通量が非常に多く慢性的な渋滞を緩和するためにも右折矢印の設置、もしくは時差信号を導入すること。
④府道223号線フタツ池交差点における横断歩道が部分的に消えているところがあります。夕刻以降になると消えている横断歩道が見えづらく危険を伴うため早急に対応すること。
忠岡町
(1)地域振興策について <継続>
忠岡駅前の店舗が相次いで閉店し、駅周辺は寂しい状況が続いております。こうしたことは地域経済にとって大きな打撃であり便益の喪失となっております。駅前エリアは商業やサービスの集積地としても重要な存在です。現在の状況が放置されることのないよう、駅前活性化に向けた検討を促進すること。
(2)安心安全な街づくりについて <継続>
大規模災害時において、情報提供はどの世代に対しても早急に行う必要があります。SNSやLINE等の情報を取得できるよう町民に登録を促進すること。
また、近年の自然災害を教訓により一層の防災・減災体制の構築を進めること。泉南地区協議会
貝塚市
(1)公共交通機関への財政支援について <継続>
市内公共交通機関(電車・バス等)の安定した運営を図るため、水間鉄道安全輸送整備費補助金・貝塚市福祉型コミュニティバス運行補助金の拡充措置を講じること。
現在、試行されているデマンド交通についての実証結果をもとに今後の山手ルートの交通の確保について説明されたい。また、貝塚市定時定路線バス実証運行されているJR東貝塚駅と水間鉄道石才駅を結ぶ路線についての実績をふまえ、どのような方向性で市民の移動手段を保障していくかについて説明されたい。
(2)ごみ集積場所の適正管理について <継続>
風雨又は小動物などの影響により、市内のごみ集積場所からごみ(可燃ゴミ、ペットボトル、プラスチック製容器包装など)の飛散が散見される。管理責任者又は利用する住民が、ごみ集積場所の清潔保持及びきれいな街づくりの推進並びに生活環境の保全を図ることができるよう、効果的な管理方法を明らかにすること。
ごみ収集場所までの移動が困難な市民に民間事業と連携したふれあい収集についての運用の実績を引き続き知りたい。(3)病児保育の浜手地区への拡充 <継続>
発熱等で看護の必要な子どもを抱えながら、やむを得ず出勤しなければならない時に利用できる病児保育は、労働者にとって安心して働くための有益な制度である。
しかし、その認知度は高くなく、必要性があるが利用には繋がっていない現状がある。現状の周知方法に加えて、パンフレットを市内の企業へ配布やSNSの活用、各子ども園からの周知等、制度の認知度がさらに高まるとりくみを検討されたい。また、現状、市内で病児保育を行っている場所は山手に一か所である。利用状況を把握し、貝塚の未来ある子どもたちに、平等にその有益性が担保されるよう、病児保育の更なる拡充について検討されたい。泉佐野市
(1)広域幹線道路の整備について <継続>
都市計画道路 泉州山手線は、大阪都心部と関西国際空港をつなぐ泉州地域の丘陵部における広域幹線道路として、地域の連携と活性化を支え大阪都市圏全体の発展に寄与するとともに、南海トラフ地震等の大規模災害時において広域的な緊急輸送ルートとなることなど多様な機能を持つ重要な路線であることからも、早期整備に向けて取り組むこと。また、併せて慢性的な渋滞が生じている国道170号線についても、国、府、警察に働きかけるなど渋滞解消に向けて取り組むこと。
泉南市
(1)市内観光資源の活性化と地元企業等への優遇について <継続>
地元住民の利用促進を図るため、市内の観光施設(泉南ロングパーク)の駐車場割引などの利用料優遇制度等の独自支援策について、構築・検討を行うこと。また地元企業・従業員の福利厚生に寄与するため同様の支援策の構築・検討を行うこと。
(2)少子化対策について <継続>
近隣市町では幼児教育の無償化実施に伴い、給食費も無償化されている自治体もあり、大阪市ではすでに実施されています。コロナ対策として臨時的な無償化はされたものの、幼児教育無償化の基本理念と近隣市町との公正・公平を確保するため恒久的な給食費の無償化を図ること。併せて、義務教育課程における給食費の無償化も図ること。
阪南市
(1)尾崎駅周辺の賑わい創出について <継続>
尾崎駅周辺は、行政、経済、文化等に関する機能が集中しているエリアであり、阪南市の中心拠点として、子育て世帯や高齢者の交流など、にぎわいの創出や快適な生活を支える拠点の形成に向けた土地利用が重要です。また、本エリアへの交流人口の増加を図り、地域の発展や活性化に取り組むことが必要です。
以上のことから、地域の強みや資源を十分に生かし、観光としての魅力を持つエリアの形成をめざし、尾崎駅周辺の賑わい創出に向け、企業・創業希望者に対しての情報発信や支援の強化に取り組まれたい。(2)尾崎駅周辺の渋滞緩和に向けたロータリー設備について <新規>
市役所駐車場及びサラダホール駐車場の敷地内にロータリーの設置や駅の利便性の確保、歩行者の安全確保のためにもグリーンラインの設置等、安全で安心して暮らし続けられる地域の形成・整備に取り組まれたい。あわせて、尾崎駅周辺整備のための十分な財源の確保及び地権者、地元住民及び鉄道事業者と協議を図られたい。
田尻町
(1)まちづくりの人材育成対策について <継続>
移住・定住施策等により、8000人の大家族プロジェクト推進が図られている中、「第5次田尻町総合計画」等に基づき「田尻町たじりっちポイント事業」が2023(令和5)年度から実施され、町民のボランティア活動の活性化と健康づくりとの相乗効果を図る施策がスタートし、世代間での交流を図るととともに各世代で多彩な人材の確保・育成が求められる。これらの新しい人材を確保するため、上記事業のほか、世代間交流事業や地域イベントなどの情報発信を強化し、地域コミュニティ活動が活性化できるように取り組まれたい。
熊取町
(1)広域幹線道路の整備について <継続>
都市計画道路 泉州山手線は、大阪都心部と関西国際空港をつなぐ泉州地域の丘陵部における広域幹線道路として、地域の連携と活性化を支え大阪都市圏全体の発展に寄与するとともに、南海トラフ地震等の大規模災害時において広域的な緊急輸送ルートとなることなど多様な機能を持つ重要な路線であることからも、早期整備に向けて取り組むこと。
また、併せて慢性的な渋滞が生じている国道170号線についても、国、府、警察に働きかけるなど渋滞解消に向けて取り組むこと。岬町
(1)企業誘致対策のさらなる強化について <継続>
町民ひとり一人が生涯安心して働き、安定した生活と充実したワークバランスを送るためには更なる企業誘致の取り組みへの強化が必要であると考える。
岬町企業立地促進条例に基づく企業誘致について、進捗状況を明確に示していただきたい。また、今後も町が求められる業種を対象としたセミナー、並びに町長による企業訪問やトップセールス等、過去の例にとられる事なく大胆な発想と手法を以て、企業誘致の更なる強化へ向けて取り組まれたい。(2)新たなみさき公園整備とみさき公園駅前の再開発について <継続>
新たなみさき公園の整備にかかる優先交渉権者が決定されましたが、将来継続的に親しまれる公園をつくることが町としての責任であると考えます。つきましては、令和4年9月28日のPFI事業者との事業契約の締結後の進捗状況や計画の詳細を明確に示していただき、また駅前開発についても、みさき公園の整備と同時に進めることが有用であると考え、計画を進める中で町民の雇用促進に対する支援を含めた取り組みに対する町としての今後の将来展望について示されたい。
さらには、南海電気鉄道株式会社のみさき公園運営事業の撤退に伴うことにより、特急の停車駅から除外されることがないよう、南海電気鉄道株式会社と正式な協議を実施していただき、今後も町民の利便性の確保に万全を期されたい。2025(令和7)年度 自治体政策・制度予算に対する要請
<要請日>
| 地区 | 自治体名 | 要請日 | 要請方法 |
|---|---|---|---|
| 堺地区 | 堺市 | 2024年11月5日(火) | 市長及び担当者との懇談 |
| 泉州地区 | 高石市 | 2024年10月28日(月) | 副市長との懇談 |
| 和泉市 | 2024年10月28日(月) | 市長との懇談 | |
| 泉大津市 | 2024年10月28日(月) | 課長との懇談 | |
| 岸和田市 | 2024年10月28日(月) | 副市長との懇談 | |
| 忠岡町 | 2024年10月28日(月) | 町長との懇談 | |
| 泉南地区 | 貝塚市 | 2024年10月16日(水) | 副市長との懇談 |
| 泉佐野市 | 2024年10月16日(水) | 副市長との懇談 | |
| 泉南市 | 2024年10月16日(水) | 副市長との懇談 | |
| 阪南市 | 2024年10月16日(水) | 副市長との懇談 | |
| 田尻町 | 2024年10月16日(水) | 副町長との懇談 | |
| 熊取町 | 2024年10月16日(水) | 町長との懇談 | |
| 岬町 | 2024年10月16日(水) | 副町長との懇談 |
<要請と回答(全体)>
| PDF 堺地区協議会 2025年度政策・制度予算に対する自治体要請回答(PDF) PDF 泉州地区協議会 2025年度政策・制度予算に対する自治体要請回答(PDF) PDF 泉南地区協議会 2025年度政策・制度予算に対する自治体要請回答(PDF) |
大阪南統一要請
(1)震災におけるインフラ整備の対応について <新規>
2024年1月1日に発生した「令和6年能登半島地震」においては、大規模な地殻変動が発生し、それらの原因により、道路網が寸断され救助隊は元より救援物資の輸送また、自治体派遣も容易でない状態となり、ボランティア活動の開始も大幅な遅れが発生する事態となりました。このような地殻変動は能登半島という特別な地形から発生したとは考えられますが、南海トラフ地震や上町断層による地震等の災害においても発生しないとも限らず、建物の倒壊等の原因による通行不可能道路となる可能性があります。自治体においては、防災計画が策定され、緊急交通路等が設定されていると考えられますが、そのような状況になった場合の早急な道路復旧等、各自治体としての対応策や予算措置についてお示し頂きたい。
| 自治体 | 回答 |
|---|---|
| 堺市 【建設局 土木部 土木管理課】 |
南海トラフ地震や上町断層による大規模な地震が発生した場合は、広域的に連携するため、救助、救援、物資輸送などの骨格となるルートの確保が重要であり、本市・国・大阪府・大阪市及び関係業団体などにより、大阪府域道路啓開協議会を設立し、大規模な道路災害時の連携・協力に向け大阪府域道路啓開計画を策定しています。 大規模な災害により重大な被災を受けた際には、緊急車両などの通行のため一車線だけでも通行確保することを目標とし、地域の建設業団体などと防災協定を締結しています。 |
| 高石市 | 道路の復旧について、災害時に迅速な対応ができるよう災害に関する協定を締結しており、倒木等障害物除去や車両の移動等を要請することができる体制となっています。 |
| 和泉市 【土木維持管理室】 |
災害時の組織体制の整備と併せ、市職員による現地確認を迅速かつ的確に実施できるよう、職員の配備体制及び参集体制を図り、大阪府鳳土木事務所および市内建設業者と連絡を密にとることで早急な道路復旧等が実施できる体制を整えています。 また、予算措置については財政部局に被害状況を密に連絡し、現計予算で対応が不可能である場合は予備費の充当や補正予算を検討する等、緊急交通路の機能を十分に発揮できるよう努めていきます。 |
| 泉大津市 【危機管理課】 |
関連部局や関連機関とともに、地域防災計画の策定において、道路管理者の役割を重視しています。具体的には、災害発生時に通行できない道路の情報を迅速に収集し、応急点検を行う体制を整えています。 また、道路上の倒壊物や放置車両の移動が必要な場合に備え、緊急交通路を確保するため、市内の民間建設業者との協力体制を構築しています。令和5年10月には、民間企業と災害時の車両移動に関する協定を締結し、早期に道路を復旧できる体制を整えました。 さらに、必要な予算措置についても計画的に進め、迅速な対応が可能となるよう努めております。 |
| 岸和田市 | 緊急交通路等の幹線道路については、発災時でも、極力健全度を維持できるよう適正な時期・範囲において舗装修繕を進めているところです。 しかしながら、地震等の災害により、緊急交通路等が通行不能となった場合には、地元企業と調整・協力のもと早急な復旧対応ができるよう努めてまいります。また、予算措置においても、柔軟な対応を行えるよう財政部局と協議・調整を進めてまいります。 |
| 忠岡町 【町長公室自治防災課】 |
本町においては、被災車両のレッカー移動による道路啓開等の活動等を目的とした災害協定を締結しており、有事の際の緊急交通路の確保を図っております。 |
| 貝塚市 【危機管理課、道路整備課】 |
災害発生直後の被害状況の把握、応急復旧及び安全点検を行うための人員確保など、必要な体制の整備に努めるとともに、指定地方行政機関、指定公共機関、陸上自衛隊などの関係機関との連携のほか、建設・土木関係業者などとの協定締結に基づく災害時の協力関係構築の推進などにより、道路上の倒壊障害物の除去・移動や放置車両の移動などの道路の啓開、復旧などの体制整備に努めてまいります。 |
| 泉佐野市 【危機管理課】 |
道路及び付帯施設が被災した場合、被災状況、緊急性、復旧の難易度などを考慮し、多量の障害物が発生した場合も含め、緊急交通路を優先して応急復旧を行い、順次その他の道路の応急復旧を行うこととしています。 |
| 泉南市 【道路課】 |
本市防災計画で位置づけられている緊急交通路おいては、道路メンテナンスに係る交付金等の活用を継続的に行っていくとともに、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するための必要な対策を検討します。 |
| 阪南市 【危機管理課】 |
能登半島地震における大規模な地殻変動により、道路網の寸断や救援物資の輸送・ボランティア活動の遅れが生じたことは、防災対策上の重要な課題と認識しています。 そのため、本市では、地域防災計画において、南海トラフ地震や上町断層帯地震などを想定し、様々な対応策を講じることとし、災害発生直後における災害応急対策にあたる緊急通行車両の通行を最優先で確保するための道路として、大阪府は広域緊急交通路を選定し、市は地域緊急交通路を選定しているところです。 |
| 田尻町 | 災害時の応急活動を迅速かつ的確に実施するため、広域緊急交通路と一体となって機能すべく地域緊急交通路について、地震発生後に人命救助や支援物資搬入等を円滑に行えるよう、迅速な道路啓開による通行機能の確保に向け、関係機関と連携した道路啓開体制等の充実を図るなどの対応を行ってまいります。 また、地域緊急交通路約1.8kmのうち、りんくうタウン内の町道約0.8km(44%)においては無電柱化、地下埋設化になっているものであります。その他の区域についても、道路上の倒壊障害物の除去、移動など、早期に道路啓開の対策の検討、予算措置については必要に応じて対応してまいります。住民へは、地震ハザードマップ、津波ハザードマップ、液状化マップにより、危険度、その対策を啓発・周知しております。また、道路網が寸断される可能性もあることから、緊急物資については分散備蓄を行っております。 |
| 熊取町 【自治・防災課】 |
震災におけるインフラ(道路網等)整備については、災害時の応急活動を迅速かつ的確に実施するため、熊取町地域防災計画において緊急輸送活動のため確保すべき道路等を選定しています。 また、災害時の通行支障に関する情報の収集体制や応急点検体制を構築し、関係機関と連携して、建物の倒壊等の原因により通行不可能となった場合の道路復旧等を早急に行い、緊急交通路の機能を十分発揮させるよう努めます。 |
| 岬町 【まちづくり戦略課、防災課】 | 本町では、『岬町耐震改修促進計画(令和2年3月改訂)』において、緊急交通路を指定し、地震時の建築物の倒壊によって避難や緊急車両の通行を阻害しないよう、沿道建築物の耐震化を促進しております。なお、本町においては、耐震診断義務付け対象路線として、広域緊急交通路である国道26号(第二阪和国道)が大阪府の計画において指定されています。また地域緊急交通路(町指定)については、耐震化を促進する路線(耐震化促進路線)として8路線を指定しています。 本町における緊急交通路(町指定)のうち通行障害建築物(耐震化促進路線)に対しては、重点的に耐震化の啓発を行います。 道路施設の復旧については、被災状況、緊急性、復旧の難易度などを考慮し、緊急交通路を優先して応急復旧を行うとともに、順次その他の道路の応急復旧を行うこととしております。なお、橋梁など復旧に時間を要する箇所を含む道路は、代替道路の確保に努めてまいります。また、災害の応急復旧予算に関しては、専決処分により速やかに対応していきます。 |
(2)各自治体による少子化対策について <新規>
本年6月に発表された2023年度の「人口動態統計」の概数による合計特殊出生率は、昨年より0.06ポイント低下した1.2となり、少子化が更に進んでいます。また、今後30年間で消滅可能性のある自治体も大阪南地域でも3自治体に増加しました。この2つの問題は少子化問題に大きく係る数値であることから、各自治体での対策として、定住促進や生産人口獲得のための独自施策や共働き支援、更に保育所における配置基準の変更に伴う対応についてもお示し頂きたい。
| 自治体 | 回答 |
|---|---|
| 堺市 【市長公室 政策企画部 計画推進担当、子ども企画課、幼保政策課】 |
妊娠・出産・子育て・教育に至るまで切れめのない子育て支援を基本として、身近な地域での子育て相談・支援の取組の充実をはじめ、こども園などの利用のしやすさや子育てに係る経済的な負担軽減など、様々な子育て施策を推進することが結果として、少子化対策にも資すると捉えています。 本市では、近年の定住・流入促進の主な取組として、令和5年度から第2子以降の保育料を所得制限なしで無償化したほか、令和7年6月からは全員喫食制の中学校給食がスタートします。また、子育て世帯が居住地の選択で重視する治安の向上についても、防犯カメラや防犯灯の戦略的な設置など、警察などと連携し取り組んでいます。 また、保育所における配置基準の変更に伴う対応については、令和6年4月に実施された国の基準改正に合わせて、3歳児を15:1、4歳児及び5歳児を25:1としています。3歳児では、国の公定価格における3歳児配置改善加算が従来から設けられており、ほぼ全ての園で実現されています。また、4歳児及び5歳児では、国の基準改正以前から本市独自の補助制度を設け、25:1とすることを可能としており、こちらもほぼ全ての園で実現されています。 今後も、子育て世代の状況や多様なニーズを的確に捉えた子育て支援の充実に努め、本市に居住されている方や今後堺に居住される方にも、本市でこどもを生み育てたいと思っていただけるよう、より安心して子育てできる環境整備に取り組みます。 |
| 高石市 | これまで、定住人口の増加や生産年齢人口の増加を図ることを課題として、各種施策を展開してきました。これらの取組を継承・発展させるとともに、国の施策と連携を図りながら、「高石市人口ビジョン」で示す施策の方向性と将来展望を踏まえ、次期総合戦略を策定予定です。これからも「地方創生」に向けた取組を進めてまいります。 |
| 和泉市 【広報・協働推進室、こども未来室】 |
令和4年度から、南部地域等への移住者・定住者に、住宅取得費等を対象とした支援金を交付するなど、移住・定住の促進に寄与する支援制度を行っています。今後も引き続き、当該支援制度はもとより、南部地域の魅力を市内外に広く発信しながら、必要な施策について他市事例等を調査研究していきます。 見直し後の配置基準による保育に対応できるよう調整をすすめていきます。 |
| 泉大津市 【こども政策課、子育て応援課、こども育成課】 |
本市におきましても、第二期いずみおおつ子ども未来プランのもと、少子化対策として、定住促進や生産人口獲得につながるよう、子育てしやすい環境づくりや、様々な子育て支援に取り組んでいるところです。子育てしやすい環境づくりとしては、市民とともに作り上げた緑あふれる公園の新設、駅前の商業施設内への図書館や子育て支援センターの設置などがあります。 また、独自の支援策については、物価高騰への支援策として、子育て応援米の支給や、7か月の乳児を持つ家庭を保健師等の専門職が訪問し育児相談を行うとともに、5万円相当分の育児用品等と交換できるギフトカードをプレゼントする「にこにこベビー訪問」、妊婦に栄養価の高い金芽米を妊娠届出の翌月から出産予定月まで毎月10㎏をプレゼントする「マタニティ応援プロジェクト」など、市独自の子育て支援事業に取り組んでいます。 これらの施策は、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援体制を構築し、子育て世帯が「この街で子どもを産み育てたい」と実感できる環境づくりの基盤となっています。特に、保健師等の専門職による寄り添い型の支援は、子育ての不安解消だけでなく、地域との繋がりを深める機会ともなっており、子育て世代の定住意向の向上に寄与しています。 保育士配置基準引き上げに伴う保育士増員についても、国の動向及び方針を把握し、関係各課と協議してまいります。 |
| 岸和田市 | 本市総合計画「将来ビジョン・岸和田」に基づき、「子育てしやすいまち」のイメージアップをめざして、子育て世代に興味を持ってもらえる情報発信に取り組んでいます。また、幼稚園と保育所の再編、保育士確保に向けた給付金の支給、夏期の臨時学童保育の実施などによる待機児童対策に取り組んでいます。 保育所における配置基準の変更については、「こども未来戦略(令和5年12月)」により示された内容であり、4・5歳児について、30対1から25対1へ(2024年度(令和6年度)から)、1歳児については2025
年度(令和7年度)以降、保育人材の確保等の関連する施策との関係も踏まえつつ、加速化プラン期間中の早期に6対1から5対1への改善を進めるというものです。 本市では、国の配置基準に則った形で4・5歳児の受入れを25対1で行っています。また1歳児ついても、既に5対1での受入れを行っています。 |
| 忠岡町 【健康福祉部健康づくり課、健康福祉部こども課】 |
町独自の施策では、妊娠を望む方へ支援の一環として、経済的負担の軽減を図るため、費用の一部助成を行う不育症治療費助成事業を行っております。また、令和6年8月より子育て支援事業の一環として子育て支援アプリ「ただおか子育てナビ」の運用を開始いたしました。子育て支援アプリでは、妊娠を希望する方から妊娠した方、子育てを行っている方を対象に、予防接種のスケジュール管理やワクチン情報、子育てに関する情報等、必要な人に必要な情報を迅速に届けることが可能であり、子育てを希望する方の住民の負担軽減、利便性向上を図る事ができます。 また、多胎妊娠は、単胎の妊娠に比べ頻回の妊婦健診が必要であり、住民の経済的負担もあることから、令和6年4月より妊婦健診費の一部の追加助成(多胎児オプション)を開始しております。配置基準の変更につきましては保育教諭を確保する必要があることから、人材確保に努めてまいります。 |
| 貝塚市 【子育て支援課】 |
定住促進や生産人口獲得のための独自施策とし貝塚市若年世帯等定住促進住宅取得補助金のほか、令和6年度から貝塚市結婚新生活支援補助金の交付を開始しました。国の補助金要件に市独自として居住誘導区域内の新婚世帯にはさらに10万円を上乗せすることにより充実した補助制度にしています。また、子育て世代向け情報発信ウエブアプリ「ためまっぷかいづか」を活用した子育て世代に役立つ情報発信のほか子育て世代向け短時間就労の機会の創出と提供を目的とした「キャリアステップかいづか」を通じ、子育てしやすい環境づくりを整備することにより、定住促進につなげています。 |
| 泉佐野市 【子育て支援課】 |
本市独自事業は以下のとおりです。 ・「出会いの機会創出事業」体験型婚活イベントを開催。令和6年8月1日から市独自の婚活マッチングサイト「さの恋」を開設。 ・「結婚新生活支援事業」新婚世帯に対する住居費用等を補助。夫婦共29歳以下は60万円、30~39歳は30万円。 ・「妊産婦タクシー利用支援事業」産婦人科などへの通院や出産・産後の健診受診等のため」のタクシー乗車券(5,000円分)を配付。 ・「多胎児家庭育児支援事業」 多胎児を養育する家庭に「いずみさの・ファミリー・サポート・センター利用 補助券」(50時間相当 40,000円分)を配付。 ・「こども医療費助成事業」こども医療費助成対象を令和4年10月から18歳年度末までに拡充。 ・「施設における給食費無償化」就学前施設における給食費無償化を実施。 ・就学前・「就学前施設における紙おむつの持ち帰りの廃止」 ・「第2子利用者負担額(保育料)無償化」小学校就学前のこどもが同一世帯に2人以上いる場合に市独自施策として2人目以降の利用者負担額(保育料)の無償化を実施。 ・「市指定ごみ袋の無料配布」2歳未満の乳幼児のいる家庭に紙おむつ用の市指定ごみ袋(20ℓ 10枚/月)を配付。 ・「各中学校区に地域子育て支援拠点を整備」(市内3カ所) 【令和6年度新規事業】 ・「子育て世帯訪問支援事業」妊娠期から出産後に体調不良等により家事や育児の支援を必要とする世帯に訪問支援員を派遣。 ・「送迎保育ステーション事業」事業開始予定 ・「就学前施設における紙おむつのサブスク事業の無償化」就学前施設において使用する紙おむつ等のサブスク事業を全額公費負担(無償化) |
| 泉南市 【政策推進室、保育子ども課】 |
第2期泉南市まち・ひと・しごと創生総合戦略(令和2年度から令和6年度)を策定し、人口急減・超高齢化という大きな課題に対し、本市として、まち・ひと・しごと創生の取組を推進し、若者が結婚し子どもを産み育てることに希望が持てる環境を整え、まちの魅力を高めることで転入促進・転出抑制に取組んできたところですが、人口減少に歯止めがかからない状況です。 今後は新たな総合戦略の策定を進めるとともにさらなる移住・定住促進にかかる施策を推進します。 |
| 阪南市 【健康増進課、シティプロモーション推進課、こども政策課】 |
不妊症及び不育症のために子どもに恵まれない夫婦に対し、経済的負担を軽減し子どもを産みやすい環境を確保するため、不妊治療等に要する費用の一部助成を実施しています。また、妊娠期から出産・子育てまで切れ目なく必要な支援につなぐ伴走型の相談支援と経済的支援を実施するため、妊娠届出時の面談後に出産応援ギフト、出産後2か月目頃に実施する「こんにちは赤ちゃん事業」訪問後に子育て応援ギフトとして給付金を交付しています。 また、本市では生産人口をターゲットとした移住・定住促進施策を展開しています。具体的には、移住定住ウェブサイトの開設やPR動画、ガイドブックの活用を通じて、市内外で移住相談窓口を設け、アンケート調査を実施しています。 さらに、人口減少対策として、移住定住施策を関係部局が連携して進めるための庁内連絡会議を設置し、情報共有を図り取り組みを推進しています。 加えて、本市の公立保育所では、国が保育士等の配置基準を見直す以前から、独自に1歳児の配置基準の軽減を行っています。 今後も、国において更なる配置基準の見直しが検討されるものと承知していますので、国の動向を注視しながら、適切な保育士等の配置を行ってまいります。 |
| 田尻町 | 本町は0~18歳到達年度末までの子どもの医療費の一部負担金助成や、3歳児から5歳児及び町立小・中学校の給食費の無償化等の、子育て世帯の負担軽減を図るための様々な施策を実施しており、ひいては少子化対策へもつなげていきたいと考えております。 |
| 熊取町 【子育て支援課、保育課】 |
本町においても、こどもの人数は年々減少し、核家族化は進む傾向にありますが、一方で、本町の合計特殊出生率(H30~R4)は1.41 で、前回(H25~H29)の1.33 から上昇しており、また、出生時から小学校入学時にかけての子どもの数は増加する傾向にあります。 このような中で、少子化対策として独自に実施している事業として、令和4 年度から産前産後ヘルパー派遣事業を実施しているほか、令和5 年度からは助産師による8 カ月児訪問事業を開始し、さらには、産後ケア事業として助産師による訪問型支援の導入を目指すなど、アウトリーチ型の支援の充実を図っています。このほか、共働き世帯を含む子育て世帯に対し、ホームスタート事業、ファミリー・サポート・センター事業を活用し、家事や育児をサポートしていきます。 保育所等における保育士の配置基準については、令和6年度より4・5歳児の配置基準が「子ども30人に対し保育士1人」から「25人に対し1人」に、3歳児の配置基準についても「子ども20人に対し保育士1人」から「15人に対し1人」に改定されておりますが、本町では全ての保育施設において最低基準は満たせているものの障がい児等配慮を要する子どもの増加に伴う加配保育士の確保に苦慮しているところです。 今後も安全安心な保育サービスを安定的かつ継続的に提供していけるよう、民間園に対する就労支援金の支給などにより、引続き保育士の確保に努めてまいります。 |
| 岬町 【まちづくり戦略室、しあわせ創造部】 |
本町の第5次岬町総合計画では、まちづくりの基本方針の一つとして定住・交流施策を推進しており、少子化への的確な対応を図るため、人口減少抑制に向けた定住施策を展開しています。 具体的には、出産祝金制度や新築住宅取得補助制度、中古住宅取得補助制度等補助事業の充実を進めてまいりました。また、未婚化・晩婚化に対する取組を推進するため、結婚を望む独身男女の出会いの場を提供する婚活事業に係る費用の一部を補助する婚活支援事業にも取り組んでいるところです。今後はさらに効果的な少子化対策、共働き支援を検討するとともに、地域住民の声を反映させた施策を展開してまいります。加えて、こども支援施策としましては、特定教育保育施設保育料を第1子半額、第2子を無償化、給食費を無償化しております。保育所の配置基準については、2024年度に行われた保育士の配置基準の見直し後の配置基準により運営を行っております。 |
(3)子ども食堂ネットワークについて <継続・強化>
子ども食堂は、食事を提供する場所のみだけではなく、地域交流の居場所づくりやコミュニケーションの場としても機能しており、現在の社会課題に対する一助となると考えられるため、更なる行政の積極的な関わりが必要であると考えることから、各自治体で担当窓口を明確化し、地域ネットワークへの連携の強化を図って頂きたい。また、実施状況においてや自治体としてのフードドライブへの支援・周知についての考えもお示し頂きたい。
| 自治体 | 回答 |
|---|---|
| 堺市 【子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども企画課】 |
【子ども青少年局
子ども青少年育成部 子ども企画課】 本市では、様々な家庭環境で暮らすこどもたちが安心して過ごせる居場所としてのこども食堂の活動の輪を広げ、支えるため、平成29年度から堺市社会福祉協議会に委託して「さかい子ども食堂ネットワーク」(以下「ネットワーク」という。)を設けています。ネットワークは、常設型フードドライブの設置、寄附の募集や食材・ボランティアなどのマッチング、交流会や研修会の開催、傷害保険などへの団体加入など、安心して継続実施していただけるよう様々な支援を実施し、こども食堂の運営団体のみならず、大学や民間企業など様々な団体が参画し、つながり、連携してこども食堂の活動を支えています。 また、新規開設時の経費補助や令和2年度から子ども食堂支援プロジェクトとして、ふるさと納税制度を活用したクラウドファンディングを実施しており、令和5年度は約1200万円もの寄附をいただきました。 今後も、子ども食堂ネットワークの枠組みを基盤として、各こども食堂が主体性を持って継続して活動できるよう様々なサポートを実施します。 |
| 高石市 | 社会福祉協議会では、その取り組みをサポートし、様々な情報や物品提供等を行い、子ども食堂同士のつながる機会も提供しております。 |
| 和泉市 【子育て支援室】 |
こども食堂など14団体の参加のもと「和泉市こどもの居場所交流会」を令和3年度から実施しています。相互理解、実践の交流や助成金やフードドライブなどの情報共有などを目的とし、令和6年末までで通算12回開催し、研修会なども実施し、地域ネットワークへの連携強化に努めています。 |
| 泉大津市 【こども政策課】 |
本市では、こども食堂を含む居場所事業の担当課が中心となり、教育委員会や福祉部局、関係団体、居場所の各運営者によるネットワーク会議を開催し、情報交換や課題の共有、市が実施する施策の情報提供のほか、居場所の運営やノウハウなどを学ぶ研修などを行っております。 加えて、地域のこどもの見守りや援助活動を行っている民生委員児童委員とも連携し、気になる子どもがいればこどもの居場所を案内してもらうなど、地域ネットワークの連携の強化を図っているところです。 |
| 岸和田市 | 岸和田市内で活動する「子ども食堂」に対し、大阪府より発信されている補助金申請の案内、民間企業等からの物資提供の案内など情報提供を行っています。 なお、フードドライブについては所管部署がございませんので回答を控えさせていただきます。 |
| 忠岡町 【健康福祉部こども課】 |
本町の子ども食堂は、現在4か所で実施しており、忠岡町社会福祉協議会を中心に子ども食堂間のネットワークを構築しており、それぞれの食堂が民間企業等から支援を受けた食材等の提供を行っております。本町としましては、食の支援として「子ども食堂開設運営費補助金」を創設し、町内において子ども食堂を開設運営しているボランティア団体等に対して補助を行っているところであります。また、教育部局との連携により、一部の子ども食堂開催の際は、子どもの居場所づくりの観点から、子ども食堂実施場所と隣接している本町児童館を開館し、小学校低学年までが利用できる小さい遊具を設置した広場や図書室、自習室を開放しております。 また、町施設を利用し実施している食堂に対しては、施設利用料等について免除の対応を行っております。フードドライブへの支援・周知については、実際行っている自治体を参考にしながら検討してまいります。 |
| 貝塚市 【子ども相談課】 |
年4回程度開催しているフードドライブで受け付けた食材などを子ども食堂のスタッフが受け取りに来る際に、子ども食堂間のネットワークを構築するための情報共有の場の設定を行っています。 また、フードドライブにつきましては、人通りの多い市役所のエントランスホールにおいて開催することにより、市民を含むより多くの来庁者に関心を持ってもらえるように努めています。 |
| 泉佐野市 【子育て支援課】 |
先述のとおり、本市ではこども食堂運営団体のネットワークを設置し、団体同士の連携を図るとともに、情報提供や物品の共同購入及び寄附物品等を実施しています。今年度はネットワーク会議を開催し、情報共有を図るなど地域におけるこどもの居場所づくりの推進に寄与しています。 |
| 泉南市 【家庭支援課】 |
令和4年度に子ども食堂ネットワークを設置し、今年度も2団体が新規加入し、令和6年10月末現在で、9団体が登録しています。 開催頻度等は団体により異なりますが、月1回から毎週実施している団体もあり、学習支援の実施等、食の提供以外の取組みや、地域の見守り機能としての役割も発揮もされています。 |
| 阪南市 【市民福祉課】 |
本市では、主に、阪南市社会福祉協議会が子ども食堂の立ち上げや支援を行っており、子ども食堂運営者や支援者等で構成する「子ども食堂ネットワーク会議」を開催し、情報共有を行っています。また、各方面からのフードドライブ等の食料支援の情報等を把握次第、社会福祉協議会や同ネットワーク会議を介し、子ども食堂運営者に情報提供・意向確認を行っています。 |
| 田尻町 | 本町における子ども食堂は民間団体が行っている1箇所のみであるため、ネットワークの構築は行っておりませんが、大阪府の補助制度を積極的に活用した運営を行っております。 |
| 熊取町 【子育て支援課】 |
本町の住民提案協働事業として実施している「子ども食堂」については、子育て支援課が担当課として、令和6年度においては南小学校区内の「こどもレストラン」、中央小学校区内の「Viento
Kitchen(ビエント キッチン)」及び西小学校区内の「ひなた食堂」において、実施団体と本町とが各々の役割のもと互いに連携を図り、こどもの食事及び居場所を提供して見守りを行い、こどもやその親が抱える悩みや、その課題に応じた支援につなぐことが出来るよう取り組んでいるところです。 また、本町では環境課が担当課として町内公共施設の窓口で食品回収(フードドライブ)を実施し、家庭で余っている食品を回収することにより子ども食堂でも活用いただくなど、食べ物を必要としている人とつなげる取組を行っています。なお、取組の周知については、町ホームページをはじめ毎年10 月の食品ロス削減月間に広報誌に掲載するとともに、町内各小学校4年生を対象に毎年行っている環境教育セミナーにおいてフードドライブの実施状況を説明し、保護者に周知を依頼しています。今後においても、関係部署や各団体同士の連携を高め円滑な取組を推進していきます。 |
| 岬町 【しあわせ創造部】 |
本町では、現在子ども食堂が構築されていない状況です。今後は、NPO、市民団体等と連携できるよう検討します。 |
地区独自要請
堺地区協議会
(1)堺臨海地区における防災対策の強化について <継続>
堺臨海地域においては、過去に台風による高潮被害が発生した。令和2年8月には大阪湾沿岸における最大規模の高潮に係る浸水想定区域が公表された。この公表結果に基づき、ここ数年で様々な策を講じているが、堤防の嵩上げ等の海岸保全施設の増強計画について、早期整備に向け大阪府に対して継続して要望すること。加えて、臨海地域における、地震・津波、高潮による人的被害を防止するための避難計画について、行労使による定期的な協議の場の設置に向け積極的に働きかけを行い、具体的かつ実効性のある施策の実現に向け取り組むこと。
回答【危機管理室 危機管理課】 |
大阪府と兵庫県が作成した大阪湾沿岸海岸保全基本計画では、近年の台風などを踏まえた海岸保全施設の整備などが重要な課題であるとされており、堺臨海地域を含むエリアの高潮対策として堤防の嵩上げなどの改良を行い、防護機能を確保する考え方が示されています。こうした中、本市は大阪湾沿岸に位置する他市町とともに、大阪府に対し、海岸の保全のための機能などの整備や近年大型化している台風による高潮などへの対策に努めるよう要望しています。 臨海地域における地震・津波、高潮による人的被害を防止するための避難計画については、「大阪府石油コンビナート特別防災区域津波避難計画」などに基づく事業所間連携の強化を促進するため、各事業所に現行の避難計画や事業所間協定に関して順次ヒアリングを行っています。今後も、大阪府と連携して事業所間連携をサポートするなど、具体的かつ実効性のある施策の実現に向けて取り組みます。 |
(2)交通バリアフリー化整備促進について <継続>
全国的に公共交通の存廃に関する報道がなされる等、交通事業者は厳しい経営状況にある。生活に欠かせない公共交通機関の代表であるバス・路面電車事業に対し、今後も国の交付金活用や市の予算措置により、引き続いての支援をお願いしたい。
特に交通弱者の生活交通確保・社会参加促進の観点に加え、バス・路面電車事業回復に向けての大きな投資でもあるノンステップバス・車両導入に対しては、国の動向に左右されず、「堺市生活交通改善事業計画」に基づき、計画通り進めていただきたい。回答【建築都市局 交通部 交通政策担当、公共交通担当】 |
公共交通を取り巻く環境は、通勤・通学利用の減少や燃料費高騰などによる運行コストの増大、運転士などの公共交通を支える担い手の不足などにより厳しい状況にあると認識しています。 そのような中、本市では、市民生活を支える生活交通の確保に向けて、満65歳以上の市民を対象としたおでかけ応援制度による利用促進やバス事業者から退出意向のあったバス路線の中で、市民の日常生活に必要不可欠な路線に対して運行経費の一部の補助、阪堺電車の軌道施設の改修や施設の高度化などのための経費の補助などを実施しています。引き続き、交通事業者と連携し、公共交通の利用促進などに取り組み、路線の維持確保に努めます。また、国の交付金の動向を注視し、事業者支援への活用を検討します。 ノンステップバスや路面電車の低床式車両の導入については、国と協調した補助を実施しており、引き続き、交通事業者、国、本市が連携し車両のバリアフリー化の推進を図ります。 |
(3)泉北ニュータウン活性化対策について <継続>
現在、堺市SENBOKUスマートシティ構想において協働で事業を推進し、企業・団体・地方公共団体などの会員を募りニュータウンの活性化を図るとしている。そのなかでモビリティWGでは新しい移動手段の導入により、幅広い世代が距離や利用シーンに応じて最適な移動手段を選択できる環境をめざすとし、AIオンデマンドバスの実証実験が行われている。現在三度目の実証実験が行われているが、利用者からは非常に好評であり、本格運用を求める声が多い。交通不便地域という事もあり、幅広い年代での利用者が増えており、地域住民にとっては必要なインフラとして認識されている。
しかし、AIオンデマンドバス事業は運賃収入だけでは採算をとるのが難しく、民間委託任せでは、不採算路線からの撤退も十分に考えられ、地域公共交通が衰退すれば地域の魅力向上や発展には繋がらないのではないか。
スマートシティ構想では官民協働を謳っているものの、このAIオンデマンドバス事業については企業任せの要素が強く、第4回堺市内バス運行連絡会でも「南海電鉄が主体となって実施するもの」として回答が示されている。
回答【泉北ニューデザイン推進室 スマートシティ担当】 |
SENBOKUスマートシティ構想においては、産学公民連携で持続可能な新たなサービスを構築することで、住民の課題解決と生活の利便性向上をめざす取組を進めています。 また、公民がイコールパ―トナーで上記取組を推進するための組織体として「SENBOKUスマートシティコンソーシアム」を昨年6月に設立し、企業、大学、地元自治会など、現在では160を超える会員の皆様にご参画いただいています。 AIオンデマンドバスの実証事業における本市の役割としては、住民理解を得るための地元調整をはじめ、国及び警察など関係機関との協議・調整、国及び大阪府に対する補助金などの申請、事業周知に関する広報PRなどを担っています。 今後も当サービスの実装に向けて、これらの役割・支援を含め、より一層、連携事業者などと一体となって取り組みます。 |
泉州地区協議会
高石市
(1)臨海工業地帯の防犯について <継続>
高砂1号線の中央分離帯は樹木の剪定を防草シートの活用で視界が広がり交通事故防止に繋がっています。樹木の適切な剪定と定期的なメンテナンスは、犯罪の隠れ家や不備な場所の形成を防ぐために重要です。また、近年、樹木の成長が早く年2回の剪定では安心・安全な歩行者の移動が困難のため、市民が快適に移動できる環境を維持するためにも、歩行者・自転車ルートにおける樹木の剪定実施回数を増やすこと。
回答 |
防草シートにつきましては、平成25年度より高砂1号線の交差点部分等、出合頭事故防止、自転車、歩行者の見通しを確保するため重点的に設置しております。 高砂地区の市道については、例年夏頃に1回、年度末にもう一度草刈と樹木剪定実施しており、さらに、令和3年度から高砂1号線のグリーンベルト及び中央分離帯において、企業への出入り口付近等、巨木化した高木の伐採を行うなど維持管理に努めております。剪定回数の増加に関しては、財政部局と協議の上、必要な維持管理ができるよう努めてまいります。 |
(2)交通渋滞の緩和について <継続>
通勤帰宅時間帯において旧26号線の「高石交差点」で左折車の混雑や信号待ち時間が長くなっており、交通流の滞りや危険な交通事故のリスクが存在しています。左折信号機や時差信号導入により、交通の円滑化と信号待ち時間の短縮を実現できると考えております。交通管理者である警察署と連携して渋滞緩和施策を示すこと。
回答【土木管理課】 |
当該要望につきましては、交通管理者である高石警察署にお伝えさせていただいており、高石警察署からは府警本部へ相談していると聞いております。 |
和泉市
(1)新住居表示の整備について <継続>
現在、旧の住居表示の地域において、救急や消防の事案が発生したときに目的地が分かりにくい、到着に時間がかかっています。また災害時における避難指示に関しても「〇×町」よりも 「〇△町〇丁目とした方が避難の必要であることが伝わりやすいと考えられます。住民の意向や要望を踏まえた上で、丁寧な対応と住民との合意が出来次第、新住居表示の整備をすること。
回答【都市政策室】 |
住居表示は、概ね市街地が形成された地区について、住所の表示を合理的で判りやすいものに改めることで、市民生活の利便性を高めるために実施しています。 今後の住居表示の整備についても、引き続き住民の意向や要望を踏まえた上で、財政面も考慮しながら、その実施時期や実施地区について検討していきます。 |
(2)教育施設の老朽設備の環境整備について <継続>
市の公立各種施設では、トイレやフェンスなど設備の老朽化が進んでいると認識しています。特にトイレについては、施設によっては早急に整備が必要な状態であると感じています。子どもの健康や成長の観点からも、利用しやすい環境整備の実行計画や予算編成について示すこと。
回答【学校園管理室】 |
老朽化状況や緊急度等を勘案のうえ、計画的に改修等を実施します。 |
(3)防災情報の周知活動拡大について <継続>
昨今の自然災害による市民の安全への懸念を抱いており、LINEなどのSNSを活用した情報展開に加え、デジタルを活用できない方々への情報伝達の強化が必要と考えます。そこで、町会未加入者やLINE未登録者へ防災ガイドマップを全戸配布するなど防災周知活動を強化すること。
回答【危機管理課】 |
市民への情報伝達については、いずみメール・LINE等のSNSを活用し、主要な情報発信手段として運用しています。 デジタルの利用が困難な市民については、屋外に設置している防災行政無線を活用し周知し、無線内容を聞き逃した場合は、電話で再度内容を聴くことが出来るサービスを設けています。 また、防災ガイドマップについては、町会等加入者に全戸配布しているほか、市ホームページに防災ガイドマップを掲載し周知を図っています。 |
(4)市民の移動手段(公共交通機関)対策について <継続>
市民の移動手段である公共交通機関について、一部の路線で減便などの運行縮小が発生していることを心配しています。市として、今後同様の状況が再発した場合、どのような取り組みを検討しているのか見解を述べること。
また現在、公共交通機関の企業では深刻な人手不足に陥っています。特に赤字路線と呼ばれる路線について、市としての具体的な対応策を示すこと。回答【都市政策室】 |
公共交通は、市民にとって、通勤、通学、買物、通院などの日常生活を支える重要な移動手段であり、市としても公共交通を維持していくことは重要であると考えています。 路線の減便、縮小、また、赤字路線等については、運行事業者と協議しながら、それぞれの役割分担を含め、対応していきます。 |
(5)交通渋滞の緩和について <新規>
「あゆみ町三丁目南」を含む、テクノステージエリアでは多くの企業が進出し企業活動を行っている一方で、周辺の道路では平日・休日に関わらず大きな渋滞が発生しています。周辺市民に大きな影響をあたえないよう渋滞緩和施策を示すこと。
回答【都市政策室】 |
あゆみ野三丁目南交差点については府道春木岸和田線と市道唐国久井線との交差点であることから、大阪府と協議調整を図り、令和4年度から渋滞緩和を目的とした交差点改良工事に着手し、令和6年7月に完了しています。 和泉市域の渋滞緩和については今後も大阪府と連携し取り組んでいきます。 |
泉大津市
(1)地域医療体制の確立について <継続>
泉大津市立病院や泉大津急性期メディカルセンターへの交通手段の確保が問題となっています。周辺の道路環境整備や市民へふれあいバスなどの交通手段の周知に向けた取り組みを行うこと。
回答【市立周産期小児医療センター 総務課、福祉政策課、土木課】 |
泉大津急性期メディカルセンターへバスをご利用の場合は、南海バス、メディカルセンターが運行する無料送迎バス、市のふれあいバスがあります。 これらをはじめ泉大津急性期メディカルセンターへのアクセスについては、ご利用される方に分かりやすいよう周知してまいります。 高齢者、障がい者、妊産婦及び乳児連れの方などが、無料で利用できる福祉バス(ふれあいバス)を運行し、福祉施設や病院などを循環しています。泉大津急性期メディカルセンターへの交通手段の確保については、泉大津市立周産期小児医療センター(泉大津市立病院)と同様に、ふれあいバスの周回ルートに令和6年12月から組み入れたところであり、11月広報などで周知を行っています。今後も必要に応じ、運行ルートの見直しなどを行ってまいります。 府道富田林泉大津線の渋滞緩和につきましては、道路管理者である鳳土木事務所へ要望の上、調整等を重ねております。 |
(2)地域振興策について <継続>
シーパスパークなど西側地域だけでなく、市全体の歴史的な資産や特徴を活かし、市民との協力を得て地域の振興と活性化を目指した施策を示すこと。
回答【地域経済課】 |
経済的な地域振興策として地元商工団体が実施するにぎわい創出事業への支援・後援を行うこと等により、駅周辺や商店街のみにとどまらず、市全体の地域振興に取り組むとともに、本市全体に点在している歴史的資産の活用を進め、市の活性化につなげてまいります。 |
(3)安心安全な街づくりについて <継続>
自転車の交通ルールの順守が市の交通安全教室の実施で向上してきています。継続実施して頂き自転車・電動キックボードのマナー面も指導を行い、地域の安全強化に向けた取り組みを行うこと。
回答【土木課】 |
自転車等の交通ルールを順守するため、春・秋の交通安全運動を通じ、市内の小・中・高校、また高齢者に向けて交通安全教室を実施しており、自転車の乗り方・交通ルールについての指導を行っております。令和6年4月には、自転車安全利用五則のチラシを作成し全戸配布を行ったところであり、広報紙やホームページでも自転車等の安全走行を呼び掛ける記事を掲載するなど交通安全教育にも努めています。 また、泉大津警察署や泉大津交通安全協会等関係機関と連携・協力し、交通安全運動街頭キャンペーンなどを通じまして、交通安全に関する教育・啓発活動を実施しているところです。 |
岸和田市
(1)防災について <継続>
ちきりアイランドにおいて、連絡橋が地震などで通行できなくなった場合に備えての避難方法や、その際その場所で働いている人数の把握手段を確立すべきと考えます。
漁連とも連携し、災害時における避難・救助活動や情報共有を強化する必要があります。市と漁連の緊密な連携を通じて、アイランド内で働く方々の退避施策や防災対策の効果的な策定を目指すこと。緊急事態に備え、住民に対する適切な指導や情報提供の体制を整えること。回答 |
連絡橋について、災害や事故等による交通遮断が発生した場合、即座に進出企業の事業活動や市民生活に多大な影響を及ぼすことになるため、引き続き、現在の2車線から4車線化へ向けて府へ要望していきます。 連絡橋以外の避難経路の確保については、関係所管課と連携しながら検討していきます。 情報提供について、防災行政無線やエリアメール・緊急速報メール等でタイムリーな情報発信を行っています。また、防災行政無線の放送を聞き逃してしまった方に対して、もう一度内容を確認できる防災行政無線聞き直しダイヤルも整備しています。 |
(2)緊急車両の到着時間短縮に向けた新住居表示と道路改善について <継続>
現在、旧の住居表示の地域において、救急や消防の事案が発生したときに目的地がわかりにくく、到着に時間がかかっています。また災害時における避難指示に関しても「○×町」よりも「○△町○丁目」とした方が避難の必要があることが伝わりやすいと考えられます。新住居表示の整備に関しては、住民の意向や要望を踏まえた上で、丁寧な対応と住民との合意が出来次第、新住居表示の整備をすること。
また、市においては、先日救急車の脱輪により緊急搬送が遅れる事態が発生いたしました。現状の道路事情や交通インフラでは、救急車が容易に脱輪してしまうような状態となっており、それによって緊急患者の搬送に遅れや支障が生じてしまうことが懸念されます。そのため、道路事情の見直しを検討し、救急車のアクセスが円滑に行える整備を進めること。回答 |
住居表示を実施することにより住所がわかりやすくなり、一刻を争う緊急時や災害時にも場所の特定が速やかになります。新たな住居表示実施に向けては、「住居表示に関する法律」に則り、歴史的経緯や地域コミュニティ等を尊重しつつ、地域住民への丁寧な説明や協議を行い、合意を得たうえで整備を進めてまいります。 また、救急車の脱輪による道路事情の件につきましては、日々、職員及び業者での道路パトロールの巡回、点検を行っているところであり、補修等の必要があった場合には、随時、解消するように努めています。今後も道路施設の点検や補修、道路舗装の修繕等を適正に行い、車両のアクセスが円滑となるよう進めてまいります。 |
(3)競輪場の処遇について <補強>
競輪場の運営について、市財政になくてはならない事業であり、中長期的に人口減少の影響を受けるものの、インターネット投票やミッドナイト競輪など無観客開催でも収益化が可能な仕組みに変容している中で、競輪事業の社会貢献活動の周知や自転車競技の魅力発信を通じて市民理解促進を図り、来場者の確保、活性化やイメージアップのための取り組みを実施すること。
また、観戦エリアの施設の老朽化が著しく進んでおり、空調や施設整備を行いお客様の動向を図り、満足度向上や地域防災、スポーツ振興、教育活動、児童・高齢者福祉など幅広い分野における地域住民サービスや社会的役割に活用するなど市民のための運営に努めること。競輪場開催業務等包括委託によって運営される公営競技場の企業の支援体制強化に努め、自治体と企業が連携し、今後も収益向上ならびに安定的な事業確立にむけ、発展可能な施策を進めること。回答 |
岸和田競輪場におきましては、お客様が安全かつ快適に投票できる環境づくりに日々取り組んでおります。これまでインターネット投票をはじめ、場内、場外車券売場など各発売形態の特性を活かした施策を展開し売上を維持してまいりました。 今後より一層、市民の理解が得られるよう、ファミリー層など幅広い世代の来場促進を図りながら、必要な施設環境維持・改善に努めてまいります。 |
(4)山林の管理について <補強>
近年の台風や集中豪雨は土砂崩れで道路が寸断されるなど被害が出ています。定期的な点検や保守作業の実施で山林の管理を徹底し、対策を講じること。
回答 |
森林経営計画の認定を受けた山林については、計画的に間伐等の整備を実施しています。それ以外の山林については、大阪府や大阪府森林組合と情報交換しながら優先順位をつけて整備を進めてまいります。 |
忠岡町
(1)地域振興策について <継続>
忠岡駅前の店舗が相次いで閉店し、駅周辺は寂しい状況が続いております。こうしたことは地域経済にとって大きな打撃であり便益の喪失となっております。駅前エリアは商業やサービスの集積地としても重要な存在です。現在の状況が放置されることのないよう、駅前活性化に向けた検討を促進すること。
回答【産業住民部 産業建築課】 |
商工会とも連携を図りながらLINE、SNSやホームページ等を広く活用し情報発信してまいりたいと考えております。 |
(2)安心安全な街づくりについて <継続>
大規模災害時において、情報提供はどの世代に対しても早急に行う必要があります。SNSやLINE等の情報を取得できるよう町民に登録を促進すること。
また、近年の自然災害を教訓により一層の防災・減災体制の構築を進めること。回答【町長公室自治防災課】 |
大規模災害発生時における情報伝達の重要性は認識しているところであり、ホームページやメール、LINE等の整備は完了しており、登録や利用の呼びかけを行ってまいります。 |
泉南地区協議会
貝塚市
(1)公共交通機関への財政支援について <継続・一部修正>
市内公共交通機関(電車・バス等)の安定した運営を図るため、水間鉄道安全輸送整備費補助金・貝塚市福祉型コミュニティバス運行補助金の拡充措置を講じること。
また、貝塚都市計画にもあります、コミュニティバスの山手ルートの便数を減らしてもデマンド交通運行を新設する重要度と必要性について説明されたい。また、高齢者運転免許返納者が買物に苦労する現状が散見されることから、支援措置として無料交通パスの配布を支援されたい。
回答に、「貝塚市社会福祉協議会が移動販売事業を実施していることから当該事業の動向を注視してまいります」とありますが、障害者の移動支援以外の移動販売事業について実績を明らかにされたい。
回答【産業戦略課、障害福祉課、都市計画課】 |
安全輸送及びコミュニティバス運行に対しての補助は継続してまいります。 デマンド交通の実証運行つきましては、今後の高齢化・交通弱者の増加に伴う移動ニーズの多様化を見据え、利用者と供給者の双方にとって、より効率的な運行サービスを提供することにより障害者や高齢者などの移動の利便性を高め、外出機会を増やしていくことを目的としています。 また、現状のコミュニティバスにつきましては、市民アンケートなどにおいて、「近くに停留所がないこと・遠回りなルートであること」を不満に思う回答が多く、狭い道にも入っていける車両の使用ときめ細かな乗降ポイントの設定・予約に応じて最適なルートを運行するデマンド交通の利便性が市民のニーズと一致していると考えています。 高齢の運転免許証返納者への支援措置につきましては、もともと運転免許証を持っていない高齢者との公平性の観点から、実施する考えはございません。 移動販売事業につきましては、貝塚市社会福祉協議会によって支援を実施しており、現在2事業者と連携し、市内町会・自治会と調整のうえ、希望のある12の町会・自治会に対し、週1回移動販売車が訪問し、どなたにでもご利用いただけることとしています。今後も移動販売支援の動向を注視するとともに、買物に苦労されている方々への支援について研究してまいります。 |
(2)ごみ集積場所の適正管理について <継続・一部修正>
風雨又は小動物などの影響により、市内のごみ集積場所からごみ(可燃ゴミ、ペットボトル、プラスチック製容器包装など)の飛散が散見される。管理責任者又は利用する住民が、ごみ集積場所の清潔保持及びきれいな街づくりの推進並びに生活環境の保全を図ることができるよう、効果的な管理方法を明らかにすること。
また、ごみ散乱防止ネット(小動物忌避ネット)の無償貸与又は助成制度の拡充を講ずること。回答に、「無償貸与や助成制度についての考えはございません」とありますが、近隣市町村の状況を説明されたい。
ごみ収集場所までの移動が困難な市民に民間事業と連携したふれあい収集について運用の実績を明らかにされたい。回答【廃棄物対策課】 |
ごみ集積場所の適正な使用につきましては、基本的に排出者の責任によるところが大きいとの考えから、利用者間で集積場所を清潔に保てる利用方法を心掛けてもらえるよう、周知に努めています。効果的な管理方法につきましては、集積場所などの状況により異なることから、開発協議や市民からの相談の機会に、個別に対応しているところです。 ごみ飛散防止ネットについて、現状では、利用者間で話し合いのうえ、購入していただいている状況です。無償貸与や助成制度を一部の近隣市で実施されていますが、現時点で貝塚市において実施する考えはございません。 なお、近隣市町のごみ悲惨防止ネットの貸与や助成の状況につきましては、堺市:無償譲渡制度あり(道路上のごみステーションを概ね5世帯以上で使用。代表者がネットを管理できる。状況調査に協力する。1か所1回限りなどの要件。)、高石市:なし、和泉市:なし、泉大津市:なし、忠岡町:なし、岸和田市:無償譲渡制度あり(ごみステーションを概ね3世帯以上で使用。代表者がネットを管理できる。1か所1枚限りなどの要件。3年経過しなければ再申請できない。)、泉佐野市:助成・貸与制度あり(おおむね10世帯以上のごみ集積所を管理する自治会または任意団体の代表者への助成(1/2、上限5万円)・折りたたみネットボックスの貸出(4~6週間))、熊取町:なし、田尻町:なし、泉南市:なし、阪南市:なし、岬町:なし、となっています。 また、ふれあい収集の実績につきましては、令和6年4月から市職員により実施しており、12月10日時点で、生活ごみの収集を支援している世帯が35件、粗大ごみの収集がのべ31件となっています。 |
(3)病児保育の浜手地区への拡充 <継続・一部修正>
発熱等で看護の必要な子どもを抱えながら、やむを得ず出勤しなければならない時に利用できる病児保育は、労働者にとって安心して働くための有益な制度である。
しかし、その認知度は高くなく、必要性があるが利用には繋がっていない現状がある。現状の周知方法に加えて、パンフレットを市内の企業へ配布する等、制度の認知度がさらに高まる取り組みを検討されたい。また、現状、市内で病児保育を行っている場所は、山手地区に一ヶ所のみである。貝塚の未来ある子どもたちに、平等にその有益性が担保されるよう、病児保育の更なる拡充について検討されたい。
回答にもありますが、引き続き認知拡大に尽力を尽くしていただきたい。回答【子育て支援課】 |
病児・病後児保育事業につきましては、平成22年10月から市内の民間の事業者に委託し実施しています。その施設の利用状況は、近隣市町の利用者も含め年間1,000人以上の受入れが可能で、浜手地区の利用者も含め希望者の受入れが概ね可能な状況のため、現在のところ新たに浜手地区への整備の考えはありません。 また、本事業の周知につきましては、現在、ホームページなどで周知しているほか、令和6年6月発行の「かいづか子育てガイドブック」に掲載し、市内の保育施設や子育て関係施設に配布しています。かいづか子育てガイドブックは作成部数に限りがあるため、企業への配付はしておりませんが、デジタル版はホームページや、子育て世代向け情報発信ウエブアプリ「ためまっぷかいづか」で閲覧可能なことから企業に対しても周知に努めてまいります。また、窓口では、委託事業者作成のパンフレットを配布しています。本事業を必要とする子育て家庭への認知が高まるようさらなる周知に努めます。 |
泉佐野市
(1)広域幹線道路の整備について <新規>
都市計画道路 泉州山手線は、大阪都心部と関西国際空港をつなぐ泉州地域の丘陵部における広域幹線として、地域の連携と活性化を支え大阪都市圏全体の発展に寄与するとともに、南海トラフ地震等の大規模災害時においても広域的な緊急輸送ルートとなるなど多様な機能を持つ重要な路線であることからも、早期整備に向けて取り組まれたい。また、併せて慢性的な渋滞が生じている国道170 号線について、国、府、警察に働きかけるなど渋滞解消に向けて取り組まれたい。
回答【道路公園課】 |
都市計画道路 泉州山手線は、泉州山手線整備推進協議会を構成する岸和田市、貝塚市、泉佐野市及び熊取町にとって、大阪南部における防災、物流、観光など様々な機能を担う重要な路線であります。本市も、大阪府の事業進捗に合わせて、沿道のまちづくりや早期事業効果発現に向けた取り組みを大阪府と連携・協力し、引き続き早期整備に向けて注力します。また、国道170号の渋滞解消につきましては、本市の実情を踏まえて関係機関へ働きかけを行って参ります。 |
泉南市
(1)市内観光資源の活性化と地元企業等への優遇について <継続>
地元企業・従業員の福利厚生に寄与するため、市内の観光施設(泉南ロングパークなど)の利用料優遇制度等の独自支援策について、構築・検討を行うこと。また、市民全体においても、同様の支援策の構築・検討を行うこと。
回答【産業振興課】 |
関係機関と連携し、検討していきます。 |
(2)少子化対策について <継続>
近隣市町では幼児教育の無償化実施に伴い、給食費も無償化されている自治体もあり、大阪市ではすでに実施されています。コロナ対策として臨時的な無償化はされたものの、幼児教育無償化の基本理念と近隣市町との公正・公平を確保するため恒久的な給食費の無償化を図ること。併せて、義務教育課程における給食費の無償化も図ること。
回答【保育子ども課、教育総務課】 |
泉南市では、以前より主食費を徴収しておらず、民間園所に対して完全給食を実施する条件で補助金を交付しております。副食費については、1号認定は従来実費徴収の対象となっています。2号認定については、1号認定および学校でも実費徴収されていること、また、これまでも利用料の一部として保護者が負担してきたことから、応益負担の考えに基づき、国の基準に沿って対応することとなりました。なお、経済的負担が大きい低所得者層等については、国の基準に沿って免除措置が講じられています。 学校給食費については、学校給食法により学校給食の実施に必要な施設および設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費のうち政令で定めるものは、義務教育諸学校の設置者の負担とすることとし、それ以外の学校給食に要する経費は、学校給食を受ける児童・生徒の保護者の負担と規定されています。 一部の自治体で給食費の無償化を実施しているところもありますが、本市の財政状況においては市単独での無償化は困難であると認識しています。 |
阪南市
(1)尾崎駅周辺の賑わい創出について <新規>
尾崎駅周辺は、行政、経済、文化等に関する機能が集中しているエリアであり、阪南市の中心拠点として、子育て世帯や高齢者の交流など、にぎわいの創出や快適な生活を支える拠点の形成に向けた土地利用が重要です。また、本エリアへの交流人口の増加を図り、地域の発展や活性化に取り組むことが必要です。以上のことから、地域の強みや資源を十分に生かし、観光としての魅力を持つエリアの形成をめざし、尾崎駅周辺のにぎわい創出に向け、企業・創業希望者に対しての情報発信や支援の強化に取り組まれたい。
また、災害に対する対応として、市役所駐車場及びサラダホール駐車場の敷地内にロータリーを設置するなど、安全で安心して暮らし続けられる地域の形成・整備に取り組まれたい。
あわせて、尾崎駅周辺整備のための十分な財源の確保及び地権者、地元住民及び鉄道事業者と協議を図られたい。回答【成長戦略室、都市整備課】 |
中心市街地である尾崎駅周辺は、重要な都市拠点であり、この尾崎駅周辺エリアの都市機能やにぎわい創出を強化していくことが課題であり必要なことでございます。そのため、エリアマネジメントを用いた、公民連携のまちづくりを進めることを総合計画に位置づけています。 また、令和6年度は、尾崎駅周辺地区を対象としたエリアの価値向上に向け、当該エリアの活性化策、アクションプランを検討するなかで、対象エリアのエリアマネジメントを具体的に展開していくため、空き家・空き店舗の状況や、対象エリアに関係する事業者や権利者へのヒアリング、道路空間の活用や歩く文化の形成検討などの業務を行っています。 今後、エリアマネジメントを進めていくことができる具体的な仕組みづくりを考えてまいります。 尾崎駅周辺は、商業等の機能が集積する本市の中心市街地であり、中心市街地としての魅力や賑わいの強化、人々が活動しやすいための環境整備等が今後の課題であると認識しております。こうした課題認識のもと、これまで歩行者の安全確保、交通の円滑化、駅前活性化の機運醸成等を目的に、尾崎駅山側道路の一方通行化と歩道整備を実施しています。 また、尾崎駅周辺に係る取組や災害時の公共交通機関の連携等については、今後も関係機関等と協議調整を行い、できるところから取り組みを進めてまいります。 |
田尻町
(1)まちづくりの人材育成対策について <継続・一部修正>
移住・定住施策等により、8,000人の大家族プロジェクト推進が図られている中、「第5次田尻町総合計画」等に基づき「田尻町たじりっちポイント事業」が2023(令和5)年度から実施され、町民のボランティア活動の活性化と健康づくりとの相乗効果を図る施策がスタートし、世代間での交流を図るととともに各世代で多彩な人材が育成されることが期待される。これらの人材を生かし地域コミュニティ活動が活性化できるように取り組まれたい。
回答 |
「第5次田尻町総合計画」において、地域づくり人材の発掘と育成、地域を支える仕組みづくりを組織横断的に取り組んでいます。その戦略の1つとして実施している「田尻町たじりっちポイント事業」により、町民のボランティア活動の活性化と健康づくりとの相乗効果を図ると共に、多世代交流や住民主体による居場所(なごみの里)づくりなどを通じて、「8000人の大家族」のコンセプトに相応しい、住民がともに支え合い助け合う、活発な地域コミュニティが形成されるようなまちづくりに引き続き努めてまいります。 また、令和7年度から地域コミュニティ活動を活性化するための住民会議の開催を予定しており、新たな地域づくり人材の発掘と育成に取り組んでまいります。 |
熊取町
(1)広域幹線道路の整備について <継続>
都市計画道路 泉州山手線は、大阪都心部と関西国際空港をつなぐ泉州地域の丘陵部における広域幹線として、地域の連携と活性化を支え大阪都市圏全体の発展に寄与するとともに、南海トラフ地震等の大規模災害時においても広域的な緊急輸送ルートとなるなど多様な機能を持つ重要な路線であることからも、早期整備に向けて取り組まれたい。
また、併せて慢性的な渋滞が生じている国道170 号線について、国、府、警察に働きかけるなど渋滞解消に向けて取り組まれたい。回答【まちづくり計画課】 |
泉州山手線については、平成27 年に岸和田市、貝塚市、泉佐野市及び熊取町の三市一町からなる「泉州山手線整備推進協議会」を設立し、これまでも泉州山手線の早期事業化に向けた要望活動を行ってきたところです。令和6年度には本協議会へ新たに3市1町の商工会議所ならびに商工会に賛助会員として参画いただき、整備推進、早期完成に向けた連携協力を図っていくこととし、令和6年7月に事業主体である大阪府に対して、要望活動を行っております。令和2年度に策定された大阪府都市整備中期計画では、(都)貝塚中央線から府道水間和泉橋本停車場線までの区間が位置付けられ、事業着手されていますが、大阪外環状線までの早期事業着手の要望を引き続き行ってまいります。 また、国道170 号(大阪外環状線)についても慢性的な渋滞解消を図るべく、大阪府に対して4車線化の早期事業着手要望を行っており、大阪府からは、現在事業中の(都)大阪岸和田南海線の完成見通しが立った段階で着手するとの考え方が示されており、引き続き、大阪府と4車線整備の進め方について検討してまいります。 |
岬町
(1)企業誘致対策のさらなる強化について <継続>
町民ひとり一人が生涯安心して働き、安定した生活と充実したワークバランスを送るためには更なる企業誘致の取り組みへの強化が必要であると考える。
岬町企業立地促進条例に基づく企業誘致について、進捗状況を明確に示していただきたい。また、今後も町が求められる業種を対象としたセミナー、並びに町長による企業訪問やトップセールス等、過去の例にとられる事なく大胆な発想と手法を以て、企業誘致の更なる強化へ向けて取り組まれたい。回答【総務部】 |
本町では、平成17年に企業誘致の優遇措置を行う岬町企業誘致に関する条例(現「岬町企業立地促進条例」)を制定以来、多奈川地区多目的公園及び関西電力多奈川発電所跡地への企業誘致に努め、多目的公園には6事業者、発電所跡地には2事業者の誘致を行い、5事業者を条例に基づく、優遇措置事業者として決定し、支援を行っています。 また、企業立地促進法や過疎法に基づく課税免除制度の導入など、積極的に支援制度を設けています。企業誘致にあたっては、町長が東京出張を利用した国等へのセールス活動や大阪府、関西電力との連携による誘致活動を行っており、企業誘致に一定の成果を見せているところです。今後とも、発電所跡地への企業誘致に積極的に取り組んでまいりますので、貴協議会においても企業用地のアピール等への協力をお願いします。 |
(2)新たなみさき公園整備とみさき公園駅前の再開発について <継続>
新たなみさき公園の整備に係る優先交渉権者が決定されましたが、将来継続的に親しまれる公園を作る事が町としての責任であると考えます。つきましては、現状いかなる展望を以て計画を進められているのか、詳細を明確に示していただき、また、駅前再開発についても、みさき公園の整備と同時にすすめる事が有用であると考え、計画を進める中で町民の雇用促進に対する支援を含めた取り組みに対する町としての今後の将来展望について示されたい。
さらには、南海電気鉄道株式会社のみさき公園運営事業の撤退に伴う事により、特急の停車駅から除外される事がないよう、南海電気鉄道株式会社と正式な協議を実施していただき、今後も町民の利便性の確保に万全を期されたい。回答【都市整備部】 |
本町では、南海電気鉄道撤退後も都市公園存続を最優先する方針とし、みさき公園が持つ集客機能と賑わい拠点としての機能を維持し、町民をはじめ周辺自治体の利用者にも親しまれる「新たなみさき公園」として、PFI事業による公園の再生に向けた取組を進めています。 令和4年9月28日には、PFI事業者と「新たなみさき公園整備運営事業」に係る事業契約を締結し、民間の資金、企画力、経営能力及び技術的能力を積極的に活用して公園を整備するとともにその後の維持管理・運営を実施することで、将来にわたって親しまれる魅力ある公園づくりに努めてまいります。また、南海電気鉄道株式会社とは、「新たなみさき公園」の整備状況を踏まえつつ、当該事業に対する協力や交通結節点としての機能の維持・向上など必要な協議を進めてまいります。 |